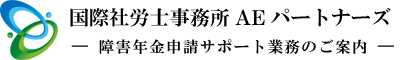厚労省が令和6年度の障害年金の不支給割合を公表

こんにちは。
茨城県桜川市の社会保険労務士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
今日は当ホームページでは少し珍しい、厚生労働省の調査データについて書いてみます。
私はもともと「不安をあおって仕事を受注する」というやり方が性に合わないもので、「障害年金の審査が厳しくなっています」などと書いたことはありませんでした。でも、今回「たしかに前年より不支給が増えているな」と思ったもので、簡単にお伝えいたします。
令和6年度の公表データは
令和7年6月11日に、厚生労働省が「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」というものを公表しました。細かい内容は省きますが、
新しく障害年金を申請したうち、 令和6年度 13%が障害等級に該当せずに、年金を受給できなかった。
種類別にみると、 精神障害 は 12.1%が該当せずに、受給できず
外部障害 は 10.2%が該当せずに、受給できず
内部障害 は 20.6%が該当せずに、受給できず
ちなみに 令和5年度は 8.4%が障害等級に該当せずに、年金を受給できなかった。
令和6年度の13%は、過去最高だった令和元年度(12.4%)を超えている。
とのことでした。
8.4%⇒13%に増加、ということで確かに増えているようです。
精神障害で不支給になったケースでは
内部障害や外部障害では、客観的な指標で判断されやすく、審査結果を見直しても特段の問題点はなかった、とのことでした。
一方で、精神障害は指標による評価がしにくい面があります。障害認定基準には、精神障害に関する「ガイドライン」が定められ、それには「障害等級の目安」が示されています。
その目安と不支給になった事案を比べると「目安より下位の等級に認定されて不支給」または「目安が2つの等級にまたがるものについて、下位の等級に認定されて不支給になった」ものが75.3%を占めていたようです。

まとめ
私も精神障害で障害年金を申請する場合は、当然ながらガイドラインや目安を参考にしています。なかでも、目安に「2級または3級」と書かれている場合など、2つの等級にまたがる場合は、特に慎重に申請書類を作成しています。
人工透析や人工関節置換など、ほぼ障害等級が決まっている(というと言いすぎ?)場合は、障害の状態について、そこまで丹念に聞き取って記載しなくても大丈夫だと思います。
でも、精神障害の場合は「どのようなことで日常生活が困っているのか?」をきちんと書かないと、そして「病歴就労状況等申立書」の「日常生活状況」など、診断書より自己判断が軽度に書かれていると、それを根拠に障害等級を軽度に認定される可能性が高いです。
他人に障害の程度が伝わりにくい疾病の場合は、特に「相手に伝わりやすく」書類作成をする必要があります。
本日は以上となります。お付き合いくださり、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)